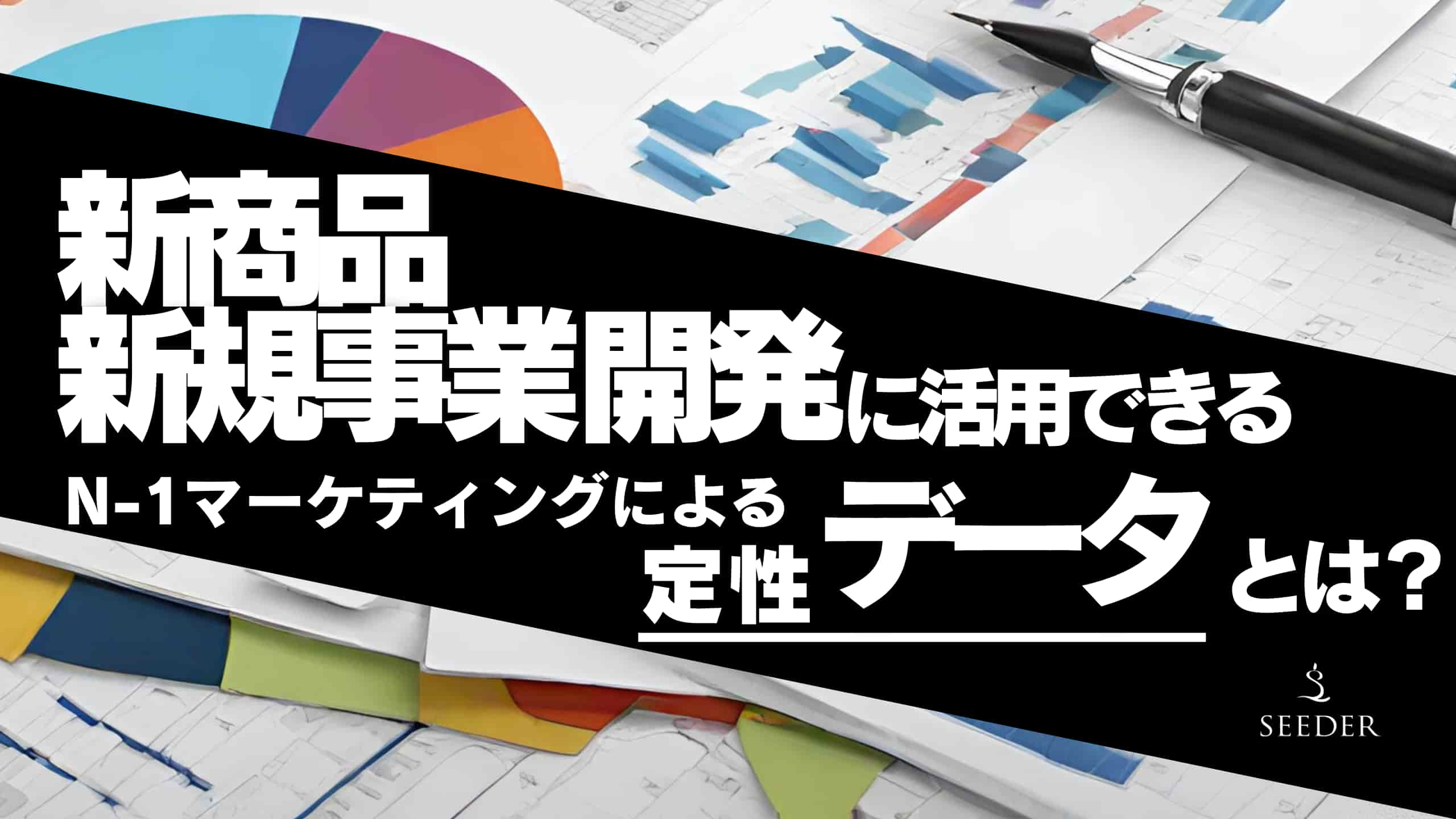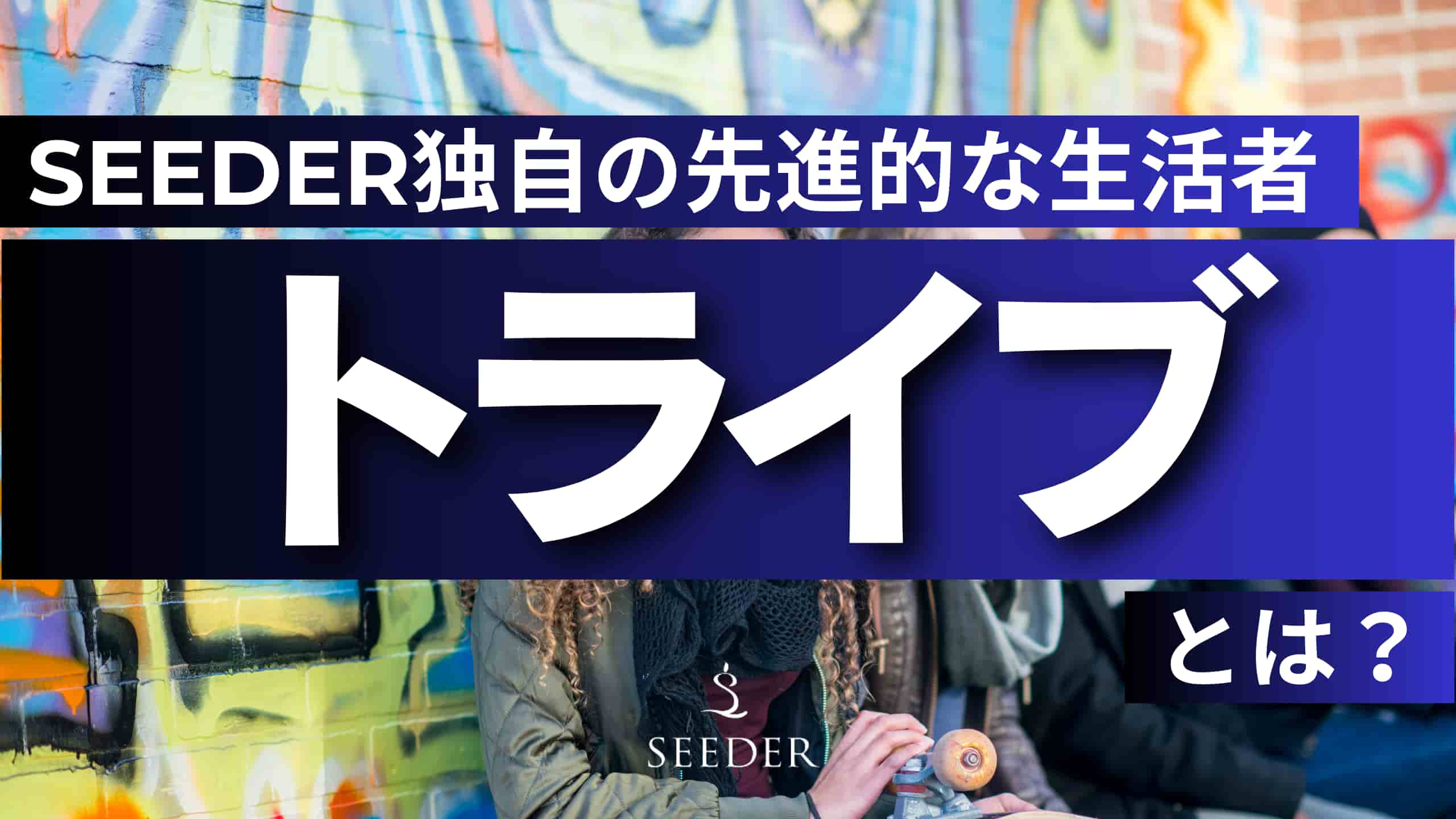デザイン思考(デザインシンキング)は、イノベーションや顧客志向のプロダクト開発において注目を集める考え方の一つです。このアプローチは、顧客の本質的なニーズを理解し、深く共感することからスタートし、新しい価値を生み出す方法論として様々な業界で活用されています。
本記事では、デザイン思考の基本的な概念から、ビジネスでの実用性、メリットやデメリット、実践方法までを解説します。

デスクリサーチをベースとした市場のトレンド分析を元に、サービス / プロダクトの改善・開発を行います。未来の生活者や市場動向を事業に活用したいクライアント様向けのパッケージとなります。
デザイン思考(デザインシンキング)とは

デザイン思考(デザインシンキング)とは、ユーザー視点に立って深く共感しながら、問題の本質を探り出し、新しい価値や解決策を創出するための思考法です。元々はデザイナーの発想法として確立されたものですが、現在ではビジネスや教育、医療など幅広い分野で活用され、顧客ニーズの多様化や複雑化に応えるアプローチとして注目されています。
デザイン思考の特徴としては、ユーザーに寄り添いながら、単なる表面的な解決策ではなく、顧客の潜在的なニーズに対応する深い共感と分析を重視する点です。このため、企業の製品開発やサービス改善の場面で導入されるケースが増えています。
アート思考との違い
デザイン思考とアート思考はどちらも創造的な思考法ですが、アプローチや目的が異なります。デザイン思考は主にユーザーのニーズや問題解決に焦点を当て、具体的な課題に対する実用的な解決策を見出すためのプロセスです。企業が市場ニーズに応える商品やサービスを開発する際に役立ち、顧客満足度の向上やビジネス成果に繋がりやすい点が特徴です。
一方、アート思考は必ずしも実用的な解決策を求めず、発想そのものを楽しむことに重きを置きます。新しい視点や自由な表現を通じて自己の内面や社会についての洞察を深め、発想の幅を広げるのが主な目的です。これにより、アート思考は自己探求や、個人やチームの視野を広げるために用いられるケースが多く、デザイン思考とは異なる役割を持っています。
デザイン思考が注目される理由
デザイン思考が注目されている背景には、現代社会が抱えるさまざまな課題が挙げられます。特に「人口減少」や「価値観の多様化」といった社会の変化により、従来の開発手法だけでは顧客のニーズを捉えにくくなっています。
こうした変化に対応し、ユーザーの本質的なニーズに応えるアプローチとして注目されているのがデザイン思考です。主な理由を2つ解説します。
人口減少
日本など多くの先進国で進行する人口減少は、企業にとって新たな課題をもたらしています。消費者の数が減り市場が縮小する中で、企業は製品やサービスの開発において、より一人ひとりの顧客に深く共感し、的確に応える必要に迫られています。
単に製品を提供するだけではなく、「顧客が本当に求める価値」を提供することが求められるため、デザイン思考が重要視されているのです。デザイン思考を取り入れることで、顧客が共感しやすい体験や感動を生み出し、リピートにつながる商品づくりが可能になります。
価値観の多様化
また、グローバル化やインターネットの普及により、消費者の価値観やライフスタイルが以前に比べて多様化しています。かつてのように、画一的な価値観に基づく製品では、すべての消費者に訴求するのが難しくなっています。
そのため、企業は一人ひとりの消費者が求める体験や価値に応える必要があり、デザイン思考がその手助けをしています。デザイン思考を活用すれば、多様なニーズに耳を傾け、顧客視点に立った商品開発が可能になります。企業はユーザーに寄り添い、彼らが本当に求める価値を提供することで、より多くの支持を得られるようになるのです。
デザイン思考がもたらすメリット
デザイン思考を取り入れることで、企業は単に商品やサービスを提供するだけでなく、顧客の心に響く価値を生み出すことができます。デザイン思考は、顧客視点に立った共感や創造的なアプローチを通じて、現代の複雑な市場環境での競争力を高めるさまざまなメリットをもたらします。ここでは、デザイン思考がもたらす具体的なメリットを見ていきましょう。
潜在ニーズの習慣的発掘
デザイン思考の大きな強みは、顧客の潜在的なニーズを発掘する習慣を組織に根付かせることです。多くの消費者は自分が何を求めているかを具体的に言葉にすることができませんが、デザイン思考では共感を通じて消費者の生活や価値観に寄り添い、本当のニーズを探ることが可能です。この手法を取り入れることで、企業は消費者の言葉の裏に隠れた欲求や課題を習慣的に発掘し、競合に対して優位性を持つ商品やサービスを開発できます。デザイン思考による習慣的な発掘プロセスは、消費者に長く支持される商品づくりに欠かせない要素といえます。
イノベーションの創出
デザイン思考は、イノベーションを促進する上でも非常に有効な手法です。この思考法では既存の枠にとらわれず、ユーザー視点で物事を考えるため、従来の発想法では生まれにくい新しいアイデアが出やすくなります。ユーザーの共感を起点として柔軟に考え、試作やテストを繰り返すプロセスにより、企業は市場のニーズに合致した革新的な商品やサービスを生み出しやすくなります。デザイン思考がイノベーションの源泉となることで、企業は持続的な成長と競争優位性を確保しやすくなるのです。
多様な意見の受容
デザイン思考の実践には、さまざまなバックグラウンドを持つメンバーから意見を集め、チーム全体でアイデアを検討する姿勢が求められます。このプロセスによって、異なる視点を尊重しながら柔軟に対応できる文化が育まれるのです。異なる視点を受け入れることで、従来の視点では見落とされがちな新たなアイデアが発見されやすくなり、組織全体のクリエイティビティが向上します。デザイン思考による多様な意見の受容は、柔軟性と適応力のある企業文化を育むための重要な要素といえるでしょう。
チームワークの向上
デザイン思考は、チーム内の協力関係を強化する上でも大きな効果を発揮します。共感を軸にした発想法は、メンバーが互いの意見や考えを尊重する姿勢を促し、円滑なコミュニケーションを築く助けとなります。また、プロジェクト全体におけるゴールを共有しやすいため、メンバー間で意見が一致しやすく、自然と連携が深まるのです。チームワークが向上することで、デザイン思考は企業のプロジェクト達成度や組織のパフォーマンスの向上にもつながります。
デザイン思考のデメリット
デザイン思考は優れた効果が期待される一方で、いくつかの注意すべき点もあります。ここでは、デザイン思考を導入する際に理解しておきたいデメリットや、どのような状況で注意すべきかについて解説します。
創造的で独創的なアイデアが生まれにくい
デザイン思考はユーザーのニーズを重視するため、自分が本当にやりたいことや独自の発想が後回しになることがあります。これにより、内発的な動機が薄れ、自分たちが思い描く独創的なアイデアが出にくくなる可能性があるのです。
たとえば、アーティストやクリエイターの中には、「顧客の要望ばかりを意識していると、自分の本来の創作意欲が薄れてしまう」と感じる人もいます。このような場合、ユーザー視点に偏りすぎず、自身のアイデアを大切にするバランス感覚が求められます。
余分なものが増える
デザイン思考のプロセスでは、ユーザーの意見を幅広く反映するため、要望に応える過程で不要な機能や複雑な仕様が追加されがちです。これにより、多機能だが使いづらい製品ができあがり、最終的に本当に必要な機能が埋もれてしまうことがあります。
たとえば、多機能なアプリが本来の使いやすさを失い、ユーザーが迷ってしまうケースがよくあります。デザインの段階で、ユーザーにとっての真の価値を見極め、不要な要素を省く判断が重要です。
プロセスよりも結果を重視してしまう
デザイン思考を導入する際、成果に急ぐあまり、プロセスの大切な部分が形だけになってしまうことがあります。特に新しい発想が求められる場面で、深みのあるプロセスが省かれ、結果的に平凡なアイデアで終わってしまうことも。
たとえば、デザイン思考を形式的に進めるだけでは、創造的な発想や新しい視点が生まれにくい状況になります。プロジェクトを進める際は、プロセスを重視し、柔軟な視点や多様な意見を取り入れることで、より良い結果につながります。
デザイン思考を実践する5ステップ

デザイン思考は、問題解決や商品・サービス開発においてユーザー視点に立ち、ニーズに即した価値を創造するためのアプローチです。このアプローチでは「共感」「定義」「概念化」「試作」「テスト」という5つの段階を踏み、アイデアを具体的な形にしていきます。それぞれのステップが、ユーザーの真のニーズに寄り添い、効果的なアウトプットを目指すための重要な過程となっています。
共感(Empathize)
デザイン思考の最初のステップは「共感」です。ここではユーザーの気持ちや経験に深く共感し、問題の本質を探ります。例えば、インタビューや観察を通じて、ユーザーが普段の生活で感じる不便や改善したい点などを理解することが重要です。これにより、ユーザーが自分の要望を表現しきれていない隠れたニーズにも気づけるようになります。
定義(Define)
「共感」で得られた情報を基に、ユーザーの課題を具体的に「定義」します。この段階では、ユーザーが抱える問題やニーズを明確化し、解決すべきポイントを特定します。問題の定義が曖昧であると後のプロセスもブレやすいため、ここでは解決目標を具体的に設定し、関係者全員が同じ目標を共有することが重要です。
概念化(Ideate)
「概念化」では、定義された課題に対する解決策を多様に検討します。ここでは柔軟な発想が求められるため、ブレインストーミングなどの手法を活用し、アイデアの数を増やすことを重視します。視野を広げた創造的な発想が、独自のアイデアにつながる場面です。既存の思考に囚われずに、自由な発想で解決策を模索することがポイントです。
試作(Prototype)
「試作」段階では、アイデアをもとに実際にプロトタイプを作成し、形にします。ここで重要なのは、完全なものを作るよりも、迅速に仮のプロトタイプを準備し、ユーザーからのフィードバックを得やすくすることです。簡易なプロトタイプを通じてアイデアの改善点を把握し、短期間で反復的に改良していくことが求められます。
テスト(Test)
最後に「テスト」段階で、ユーザーにプロトタイプを試してもらい、実際の使用感や不具合を確認します。このフィードバックに基づいて、プロトタイプをさらに改善し、ユーザーにとって使いやすい製品やサービスに仕上げます。ここで得られる改善ポイントは、次のアイデア開発や設計にも活かされ、全体としてユーザーの満足度が高まることを目指します。
デザイン思考に使えるフレームワーク
デザイン思考を効果的に進めるためには、適切なフレームワークを用いることで、問題発見から解決策の導出までを効率的に行うことができます。ここでは、デザイン思考に特に役立つフレームワークを紹介し、それぞれの特徴や使い方について解説します。
ペルソナ・共感マップ
ペルソナ・共感マップは、顧客やユーザーを深く理解するためのフレームワークです。ユーザーの「考えていること」「感じていること」「行動」「発言」「ストレス」などを視覚化し、ペルソナとして描き出すことで、ユーザーが何を求めているのかを詳細に捉えることができます。
SWOT分析
SWOT分析は、主に「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の4つの観点から自社やプロジェクトを多面的に分析する手法です。デザイン思考においては、解決策を検討する段階でこの分析を活用することで、競争環境や市場の課題を把握し、適切な戦略を立てる基盤となります。
リーンキャンバス
リーンキャンバスは、9つの要素に分解してビジネスモデルを構築するフレームワークで、短期間でプロジェクトの全体像を把握できます。デザイン思考の実践では、特に新しいアイデアやサービスを検証する際に用いられ、仮説の検証や改善を繰り返しながら、価値提案や課題解決のポイントを明確にできます。
3つのレンズ
3つのレンズは、デザイン思考の開発段階で有効なフレームワークです。「有用性(Desirability)」「実現可能性(Feasibility)」「持続可能性(Sustainability)」の3つの視点で検討することにより、製品やサービスがユーザーにとって有用で、かつビジネスとして成立するかどうかを見極められます。特に、長期的な視点でイノベーションを促進したい際に役立ちます。
ダブルダイヤモンド
ダブルダイヤモンドは、2つの「発散」と「収束」を組み合わせたプロセスで、問題の発見と解決の両面を段階的に進めるフレームワークです。「正しい問題の発見」と「正しい解決策の導出」を目指し、デザイン思考のプロセスにおける「共感」「定義」「概念化」「試作」「テスト」を円滑に進めるための基盤となります。
まとめ
デザイン思考はユーザーの視点を軸にした思考法であり、企業がユーザーインサイトを深く理解し、価値ある商品やサービスを創出するための強力な手法です。今回ご紹介したとおり、「共感」から「テスト」までのステップを踏むことで、ユーザーにとっての真のニーズを明確にし、より深い価値を提供できるでしょう。
また、デザイン思考をさらに効果的に活用するためには、単なる数値データではなく、ユーザーの定性的なデータ分析が重要です。私たち、SEEDERの「トライブ」では、特定の個人の行動や価値観に深く踏み込むことで、生活者の隠れたインサイトを明らかにし、それを事業や商品の方向性に生かしています。
SEEDERでは新規事業開発に伴うリソースや知見の不足に悩む企業様を、伴走支援というかたちで支援しています。事業の開発や改善に関するお悩みをまずはお気軽にご相談ください。【お問い合わせはこちら】